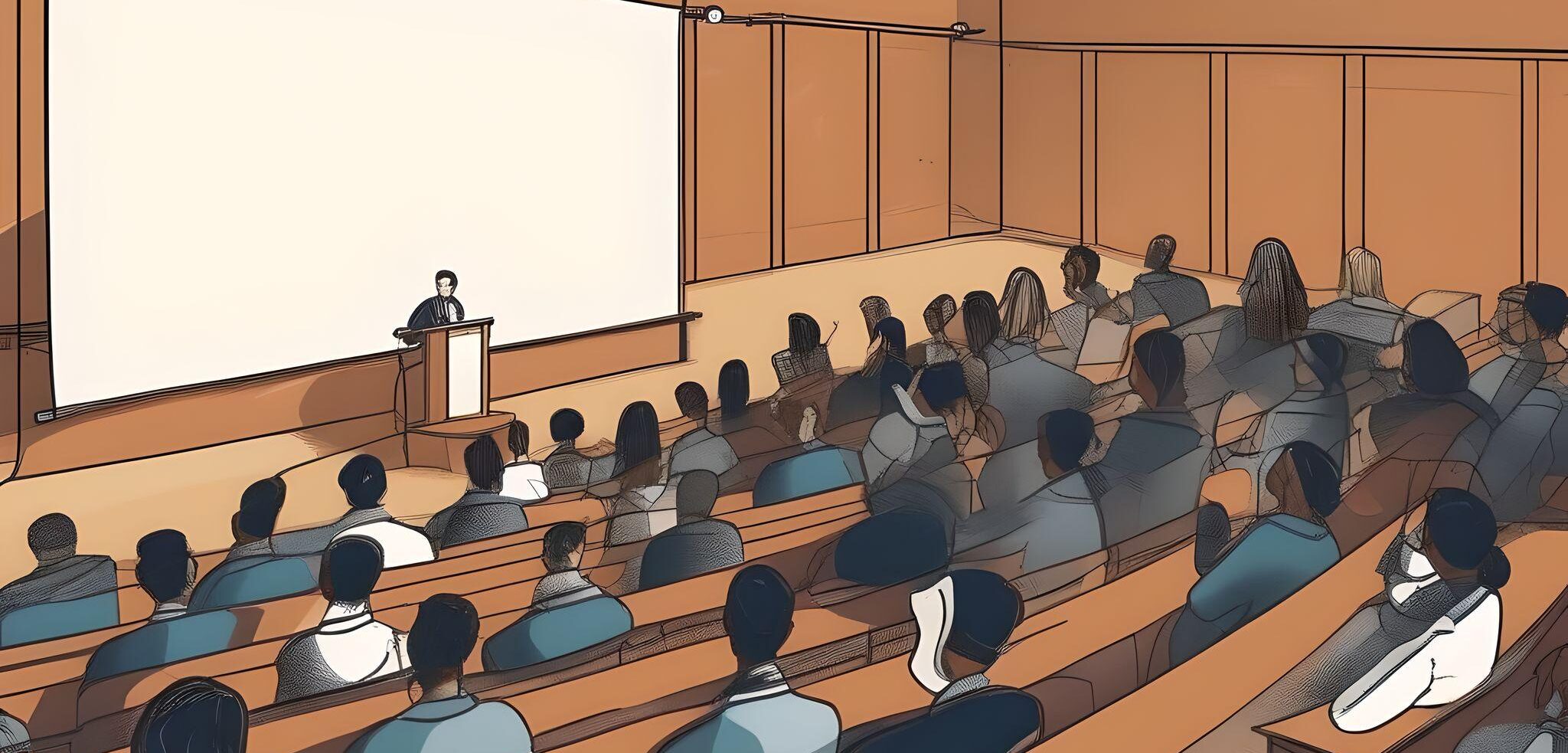マイナ保険証以外のマイナンバーシステムに関する意見を紹介しようと思う。まずはこのホームページに書いた過去の記事の紹介から。
記事の中でも述べたが、「住民票や印鑑証明などの行政情報をデジタル情報のまま提出」できるようにならないだろうか? マイナンバーシステムによりコンビニで住民票が取れるようになった便利さは感じている。それをさらに進めて、マイナンバーを知らせるだけで提出先が必要情報(住民票などのデジタル情報)を受領できるシステムは可能なような気がする。そうすれば、提出先で書類を保管したり、その書類から手入力する手間も省けるのではないだろうか? ただ、本人の承諾をどのように確認したら良いか今は思いつかない。マイナンバーを知られることで個人情報が漏洩することは防ぐ必要があるのだが。
マイナカードが免許証として利用出来るようになった。一方で、免許証の有効期限がマイナカードでは確認できないと指摘する声もある。私は、免許証をはじめとするマイナンバーカード情報をスマホで表示できるように早くした方が良いと考えている。JAF会員証や身障者用ミライロをはじめ、様々な会員証情報をスマホで表示させ、それが正式な会員証として認められるようになってきた。免許証もスマホ表示したものも正式なものとして扱ってもらうことはできないのだろうか? そうすれば、有効期限も表示でき、現在の免許証は必ずしも必要なくなるように思う。法律的な問題もあるだろうが、早くスマホがマイナ免許証として使えるようになることを望む。警視庁は東京都管轄なので、意見を聞いてみたいと思っている。
また、様々な書類にマイナンバーを書いて提出する際に、マイナンバーカードのコピーの添付を求められることがある。なぜコピーの添付が必要なのか常々疑問に思っているのだが、何か理由があるのだろうか?
ともかくみんなでマイナンバーシステムを使うようにして、不備があったら修正を加えながら育てていくという考え方が重要だと思っている。今すぐに不備のない、全て満足できるものはできないが、5年後、10年後に確実に便利で使いやすいものになっていることを期待している。