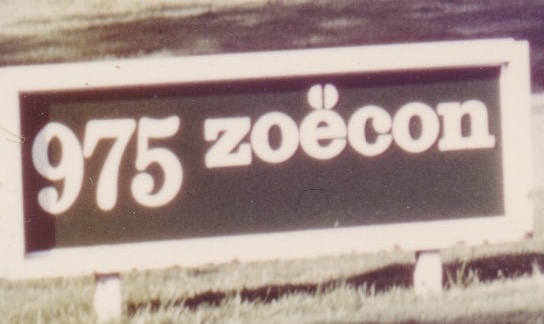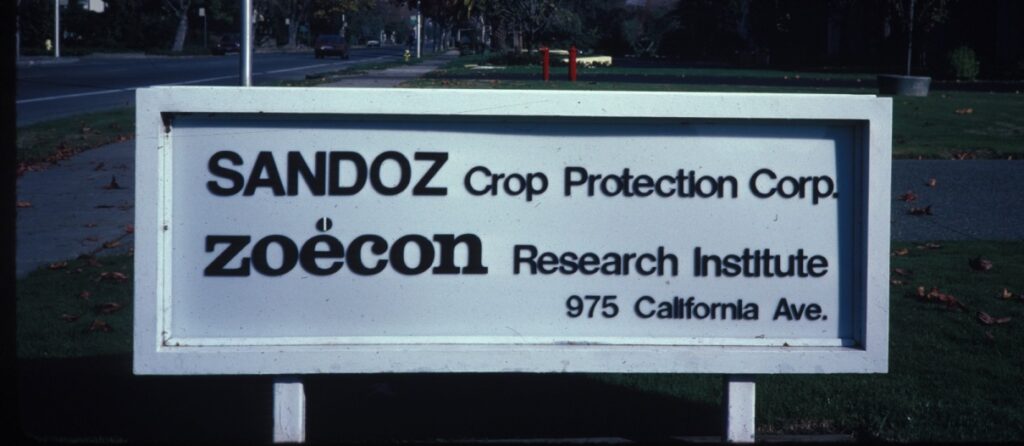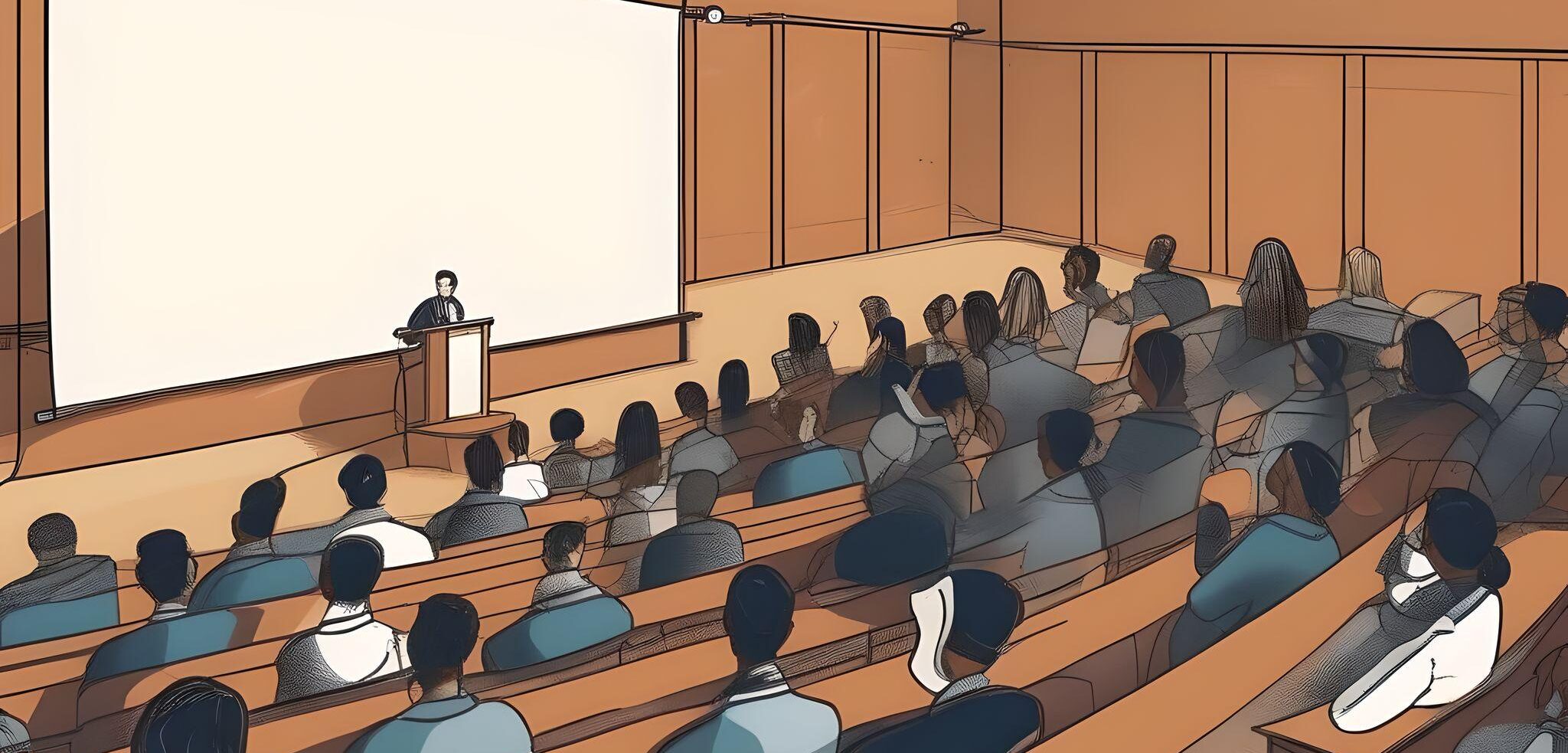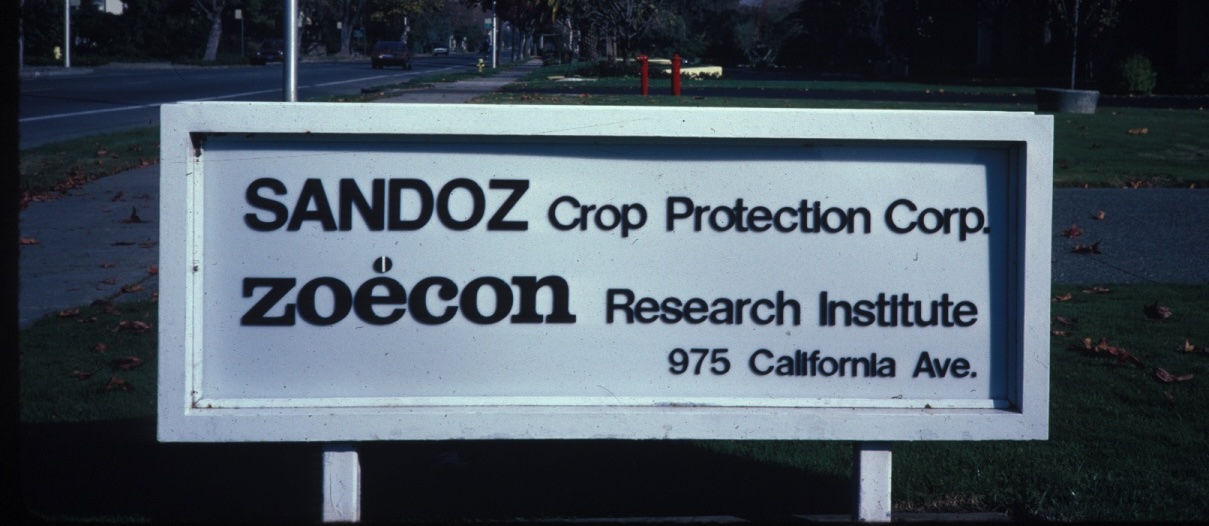このところトランプ関税の話題が毎日TVで報道されている。少し前はハーバード大学への留学生受け入れ拒否や研究機関への補助金カットだった。いったいアメリカはどうなったのだろうか? 40年前に2年間留学した時の経験や個人的に手に入れた最新情報も踏まえて、私のアメリカ(人)に対する思いや考えを2回に分けて紹介したい。独断と偏見に満ちた内容を自由に書きたいので、事実とは異なるかもしれないことを最初に断っておく。
私が40年前の留学当初にアメリカで感じたのは日本とのカルチャーの違いだった。気を回してくれることはなく、自分が主張して頼まないと助けてくれることはなかった。留学当初「independent」になるようにと何度も言われた。今考えると、実験機器の使い方をはじめ何でも直ぐに助けを求めようとしたように思う。しばらくすると話さなくても(研究)生活に支障がなくなったし、日常会話ではあまり不自由を感じなくなったが、感情を表しながら思っていることを話せるようには最後までならなかった(アラタ体抑制ホルモンの記事を参照)。
形式的な挨拶を交わすことにも違和感を感じた。「How are you?」と話しかけられ、疲れているので「tired!」と答えると怪訝な顔をされ、「I’m fine.」と答えないといけないことを学んだ。また、日本では「first name」で呼び合う仲になったと言うが、それが普通であり、良好な人間関係を示すものではない。私を「Kataoka-san」と呼ぶ著名なアメリカ人教授がいるが、彼は私に尊敬の念を持っているからだ。いつもは「Hi, Jim」と答えるが、研究について真剣に語る時は私も「Prof. Truman」と呼ぶことにしている。「first name」で呼び合うことを「胸襟を開いて話ができるようになった」と勘違いしない方が良いと思う。また、ちょっとうまくいくと「good job!」とやたら褒められ、最初の頃はからかわれているのかと思った。気軽に褒める行為は楽天的なアメリカ人気質なのだろう。本気で褒めていないことは知っておく必要がある。一方で、感情的に相手を責め、自己主張するのもアメリカ人の特徴のひとつである。いつもは温厚な私のボスSchooley氏が自動車整備工場で激高して抗議する姿を見た時は驚いた。
私が留学したのはZoecon(ゾエコン)社という農薬関係のベンチャー企業で、スタンフォード大学の教員仲間が設立した研究所だと聞いていた。世界中の農薬や昆虫ホルモン研究者の間では有名なベンチャー(企業の)研究所で、ゾエコンという名前を私も学生時代から知っていた。研究環境は大学と同様に自由で、研究内容や進め方もほぼ制約がなかった。Schooleyをはじめ昆虫ホルモン業界では著名な研究者が複数所属していたし、大学との共同研究も盛んであった。企業としては珍しくポスドク(博士研究員)制度があり、ポスドクにはアメリカ国内の様々なところを訪問していろいろな体験ができるように年間30日の有給休暇や、卒業直後でも赴任できるように旅費を負担してもらえるシステムがあった(私は日本航空便を希望したら、予約の都合でビジネスクラスを使って渡米することになった)。また、研究費も潤沢で、試薬や消耗品の注文は上司(Schooley)に依頼するとほぼ問題なく発注できたし、赴任数ヶ月後には私の希望で、先々必要になる数千万円するペプチドシーケンサーの購入も認めてくれた(この機器のお陰で私や同僚は多くの研究業績をあげることができた)。また、世界中の大学教員を旅費や謝礼を支給してセミナーに招聘するなど、アカデミックな雰囲気を大切にする研究所であった。
ところが、1年半後にスイスの製薬会社サンド社がゾエコンを買収し会社名をSandoz Crop Protection Corp. にして、自社の農業部門の研究所「Zoecon Research Institute」にした途端に雲行きがおかしくなった。その話が起こる直前に、ボスのSchooleyから「ポスドクではなく正規職員にならないか」との話があった。3つのペプチドホルモンを1年あまりで精製・構造決定した私の研究遂行能力を認めてくれたのと、Schooleyが統括する部門の正規職員のポジションがしばらく空席であったためだと説明された。「数年のうちに日本に帰国しようと考えているので、断る」と答えたが、「正規職員になってもやめるのはいつでも大丈夫だ。何も条件なしに給与が倍になるだけなので良い話だよ。」と言われ、少し考えて返事をすることにした。また、ちょうどその頃、利根川進氏がノーベル生理・医学賞を受賞した。受賞対象の研究はスイスの製薬会社ロッシュが出資したバーゼル免疫研究所での研究成果が大きく評価されていた。