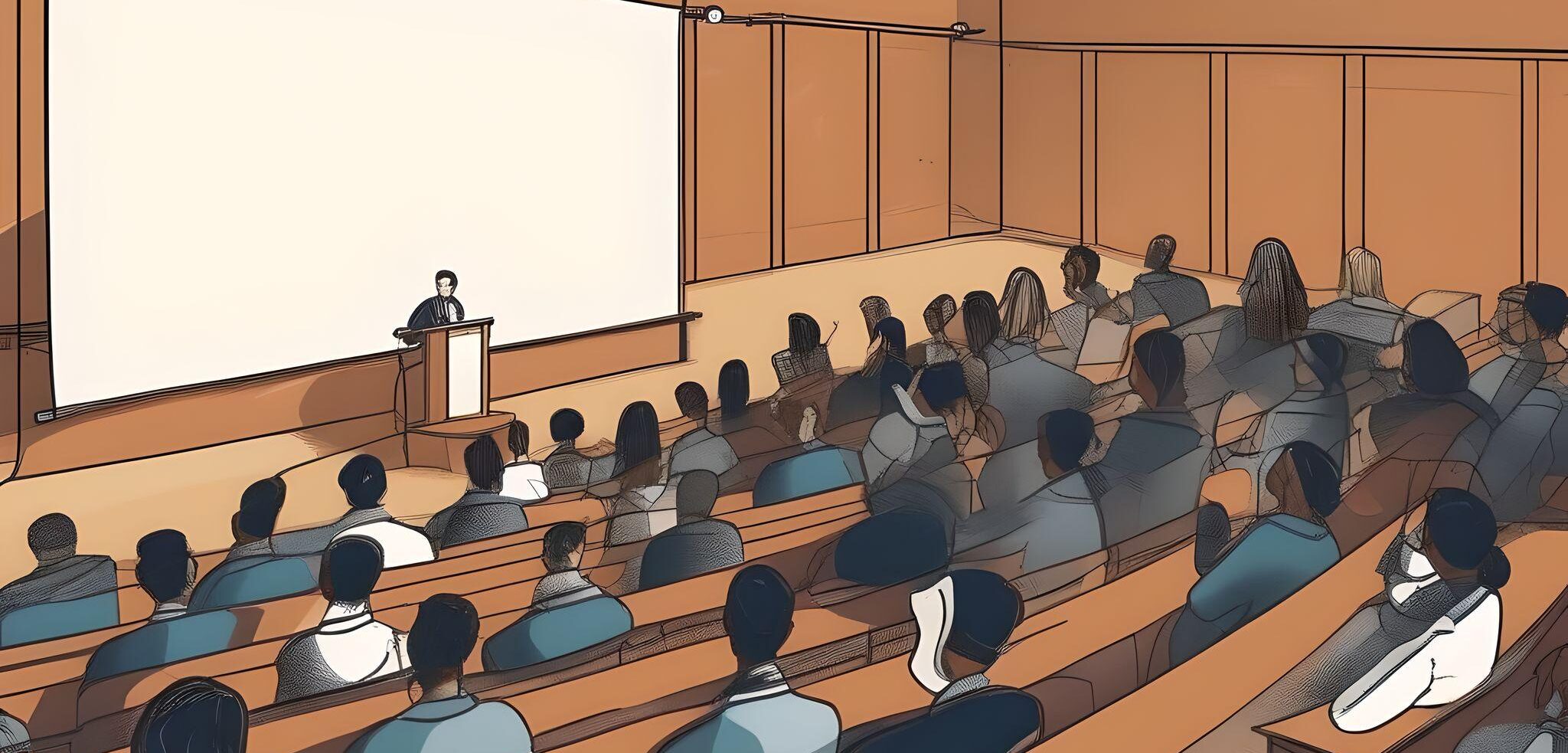それにしても暑い。昨年も同じだったような気がするが、今年より暑かったかどうか覚えていない。数日前に郷里の友人がグループLINEで「ワレモコウや自生のヤマキキョウも花を付けて、秋の気配も感じられました」と連絡してきたが、別の友人が(暑さで気が立っているのだろう)「秋の気配? 日本に秋なんてもうないですよ。9月は夏です。まだまだ暑い日が続きますよ!」と反論してきた。人間は主に気温で季節を感じるが、生物は主として日長で季節を感じとっているということを知っているだろうか? 8月下旬なのに気温は高いままだが、夜明けは夏至の頃に比べて1時間ほど遅くなっているし、日暮れも早くなっている。ベランダのフジバカマも花芽を付けはじめ確実に秋に向かっているような気がする。生物にとって季節(秋)とは何だろう?
ある日長以下(短日)になると花を付ける菊では、夜間に電灯を付け昼間を長くすると花芽ができるのを遅らせることができる。昆虫も季節ごとに現れる種類が違う。春の女神「ギフチョウ」は早春に舞い、決して夏にはいない。クワガタもカブトムシも夏のものだが、クワガタの方が少しだけ早い。蝉の鳴き声も夏の風物詩だが、種類によって少しずつ時期が異なる。赤とんぼは夏の終わりになると見ることができる。季節によって見かける昆虫が違うのは、日長を感じて成長(脱皮や休眠)をコントロールし、羽化の時期が決められているためだ。では、気温は全く関係ないかというとそうでもない。新潟のある地域のギフチョウは、20年前にはゴールデンウィークの頃に羽化していたが、温暖化の影響で年々早まり去年は3月中旬に観察された。ところが、今年は4月中旬まで雪が残り、気温も低かったためギフチョウの飛翔がかなり遅れた。
昆虫にとっての季節を考える時、食草や吸蜜花になる植物の生長にも着目する必要がある。昆虫の絶滅種が増えている原因のひとつとして、昆虫とこれら植物との間で季節の感じ方が少しズレてきているためではないかと私は思っている。植物は日長を、昆虫は気温の方をより優先しているのではないかと勝手に考えている。そのために、本来は同じ時期に羽化、芽生えや開花するはずの生物たちが、少しずつ時期がズレ始めているのではないか? そのために昆虫は食草や吸蜜花である植物を利用出来なくなって次世代を残せなくなっているのかもしれないと考えている。それぞれの専門家から意見を聞いてみたいものだ。
一方で、この暑さでは植物も昆虫も季節を感じる前に、干からびてしまうのではないかと心配している。