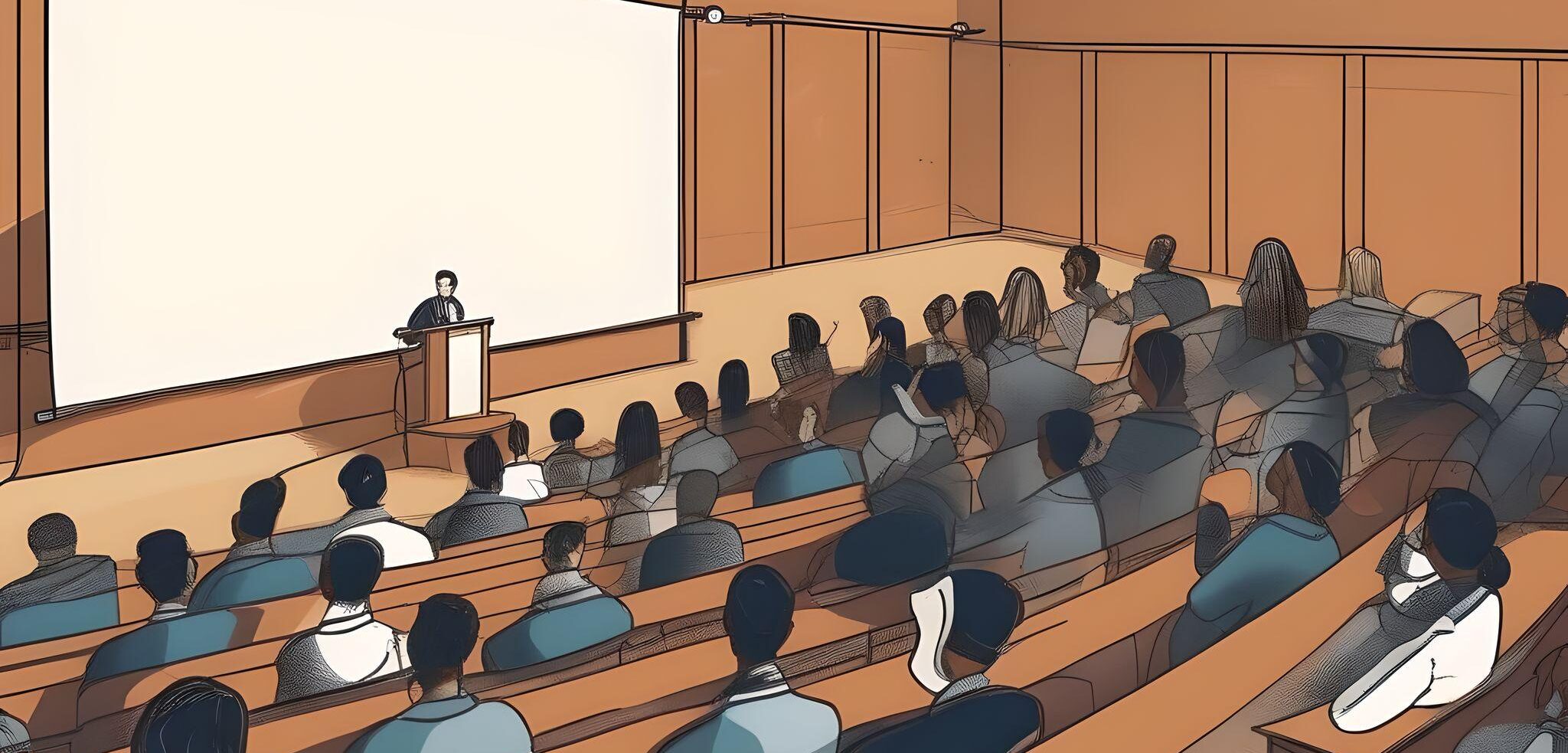2025年4月7〜8日に「春の女神 ギフチョウ」観察のために一泊二日で妻と新潟へ出かけた。昨年もトライしようとしたが、思いついたのがゴールデンウィークで、遅いとのことで諦めた。今冬の新潟県は雪が深く、さらに、4月になっても気温が低くて天候が悪く、いつが観察に適しているのか迷っていた。噂では昨年より2週間以上遅れるのではとのことだったが、このところ忙しく、また今後も忙しくなるかもしれないので、今しかないと4月7〜8日に、その時期に観察できそうな場所へ出かけることにした。
20年前のゴールデンウィークの時期にギフチョウ観察スポットを教えてもらった、いつも情報をくれるMさんに尋ねたが、もう10年以上ギフチョウ観察には行っていないので、時期も場所も分からないとのことだった。そこで、Mさんに無理をお願いして現役のムシヤのTさんを紹介してもらい、ポイントをいくつか教えてもらった。そのうちの一カ所で幸運にもギフチョウを観察することが出来た。当日も気温が低くて天候も不安定で、二日目の昼前1時間弱の晴れ間に4匹だけ目撃できた。残念ながら、イメージしていたギフチョウの集団乱舞は見ることができなかった。そのうちの一匹を妻がネットで捕獲して、放蝶する様子をビデオ撮影した。羽化したての(たぶん)雄だった。その前後にも少し離れたところを飛んだり、止まっている個体(3匹)を見つけたが、かなり警戒しているようで、近づくと直ぐにどこかに飛び立ってしまった。近くに咲いている吸蜜花であるカタクリの紫色の可憐な姿も写真に収めた。
ギフチョウは「春の女神」と呼ばれ、雪解けとともに飛翔する「春を告げるチョウ」としてマニアの間でも人気のチョウである。私の郷里、岡山県では県内の全ての生息地で絶滅したと聞いている。食草を採集して人工飼育で増殖させようという過保護な保護活動が逆に自然界の個体数減少を加速させたのかもしれない。保護活動では、チョウそのものだけではなく、幼虫が食べる食草や吸蜜花の保護にも注意を払うことが重要だと私は考える。
来春もここへ来てギフチョウを見ようと思いながら、気持ちがよい自然を満喫したあと、4時間あまり帰京のために車を走らせた。高速道路から見た景色は、至る所にまだ雪が残っていて、当初考えていた20年前の観察スポットは完全に雪の中であった。