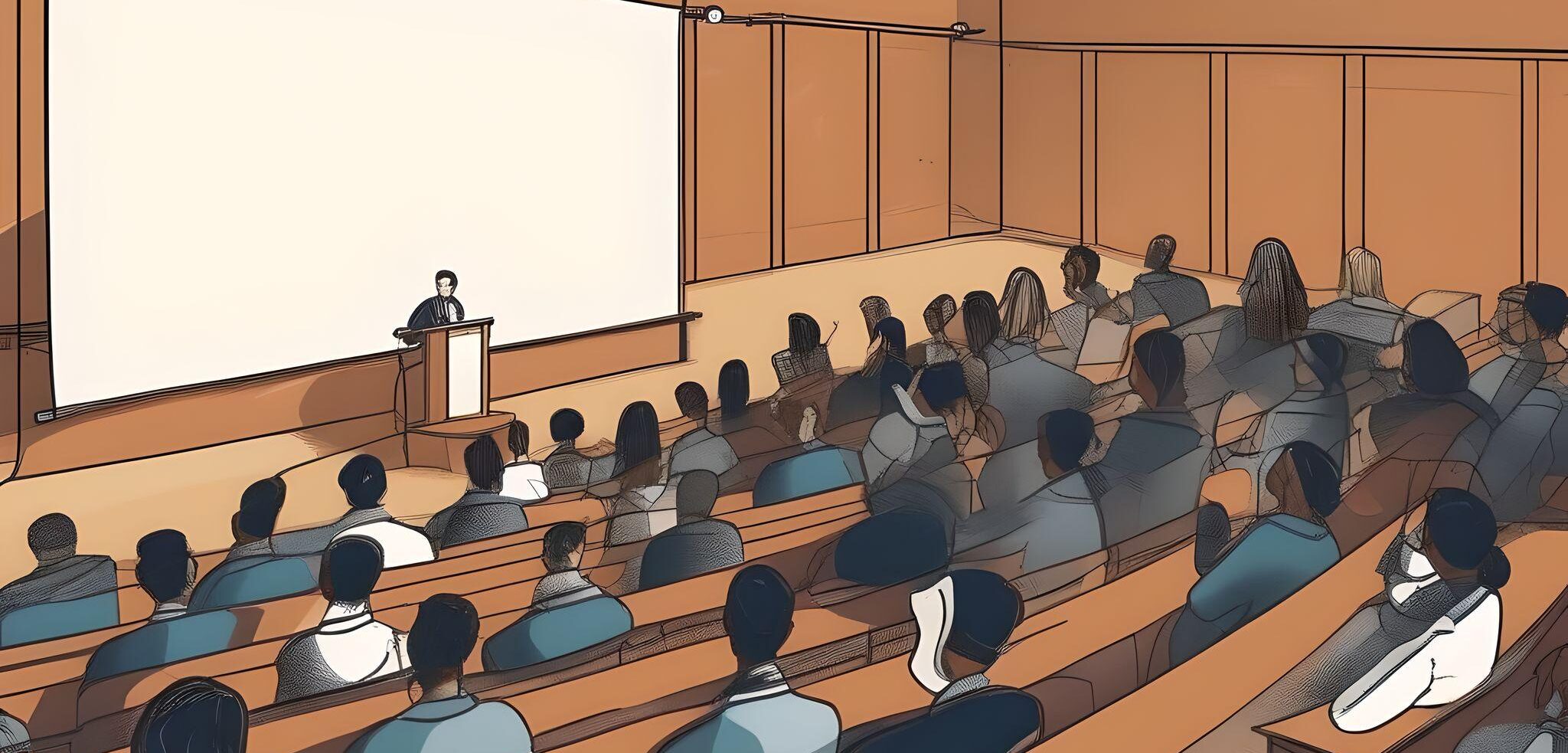まずは、関連するこれまでの記事の紹介から。
一年前の退職後の「6月(4、5月分の支給)の年金振込額が本来の1/5程度になった」事件を先に紹介した。予定していたお金が予定した日に入金されないと年金生活者には辛かった。担当者に「あなたも退職の時にこんなことが起こると、嫌な思いをするよ」と伝えたが、全く意に介してくれなかった。今は若くて退職や年金など考えもしないかもしれないが、私はマイナンバーシステムを整備することでこのような問題も防ぐことができるのではないかと考えている。
私は「高齢者にこそデジタル化が重要である」と自己PR動画で主張したが、高齢者がすぐにスマホを使いこなせるようになるとは考えていない。私を含めた60才から75才くらいの世代が、デジタル化が可能なボーダーラインの人達だと思っている。我々の世代は、ワープロ、マイコン、携帯電話、テレビゲームが開発された時代に生きてきた。その時々で新しい技術の取扱説明書を読んで、何とか使えるように努力した。ところが、技術革新は我々の能力を遙かに超えて進歩している。私はガラケイからスマホに3年ほど前に変えたが、使いこなしているとは言い難い。LINEも友人や息子に言われて2年ほど前に始めた。ホームページへの記事アップも一年かけてやっと自分でできるようになった。ツイッター(X)のアカウントは5年ほど前になぜだか作っていたが、その存在を最近まで忘れていた。YouTubeの配信もこの機会に始めようと思ったが、後援会のメンバーがサポートしてくれることになったのでやめた。Zoomはコロナ禍で講義や会議のために必要になり、今ではある程度使えるようになっている。年齢とその置かれた立場によって違いはあるが、我々がデジタル化可能なボーダーの世代なのは間違いないと思っている。
何を言いたいかというと、ある年齢までは新しい技術を簡単に身に付けられるが、ある年齢を超えるとかなり努力しないと難しくなり、さらに年齢が進むとほぼ絶望的になる。つまり、ある年齢以上の高齢者に、若い人と同じようなデジタル化を進めようとしても、教わる高齢者にとっても教える側にも苦痛でしかなく、最終的に使いこなせるようになるとは思えない。若い人(うちの息子も含めて)にそのことを理解してもらいたい。
先日銀行で見かけた光景である。80才を超えた方が口座開設を希望されていた。行員の方はスマホで申し込むように指示していた。高齢者の方はスマホを手に何とかしようとしていたが、どこかの画面で入力を間違えて立ち往生したようだった。行員の方が戻ってきて少し手助けしたら画面を進めることができたようだ。その後もその繰り返しが一時間近く続いた。その高齢者が途中で一言「書類で書けるなら簡単なのだが...」。その方は最終的に口座を開設できたかのだろうか? 「法律か銀行の方針か分からないが、紙媒体(アナログ)でも口座開設ができないか」と思ってしまった。
他にも、私がうまく使いこなせていないサービスや、あれば良いと思うサービスを書き連ねておく。
1. タクシーの配車アプリ(近くまで呼べるが、自分が居るところに来ない。道の反対側だったり、お店の反対側の道だったりする。)
2. 私は退職時にいくつもの退職関係書類を提出した。ひとつの書類提出だけで手続きが全て完了できていれば、私のような問題は起きなかったと思っている。
3. 手続きの多くが本人限定で、時にはスマホのカメラ機能を使った本人確認が必要なものが増えてきた。ところが、高齢者はそれに対応できない。本人に限らず、本人の承諾を受けた家族に委任できるシステムはできないだろうか?
4. 本人が動けなくなった時に、家族や親族への緊急連絡や、信頼できる知人への緊急連絡、さらに登録されたスマホで住居の解錠ができないだろうか?
5. 死後に必要な手続きが「死亡届」が提出されるだけで自動的にできないだろうか? サブスクの解約や、銀行や証券口座情報などが相続人に伝わり、解約・相続できるシステムはできないだろうか?
まだまだあるが、マイナンバーシステムをうまく活用することで対応可能な気がする。個人情報の漏洩や詐欺行為を警戒するなら、そのサービスに登録しなければ良いように思う。便利さを優先するか、危険を回避するかの選択は本人にあって良いように思う。そのためにもシステムの構築を早く進める必要がある。
今すぐには無理にしても、5年後から「80才以上でスマホを使える高齢者」が増えていけば、高齢者のデジタル化が徐々に進むことになると考えている。確実に結果を残すためには焦ってはいけない。