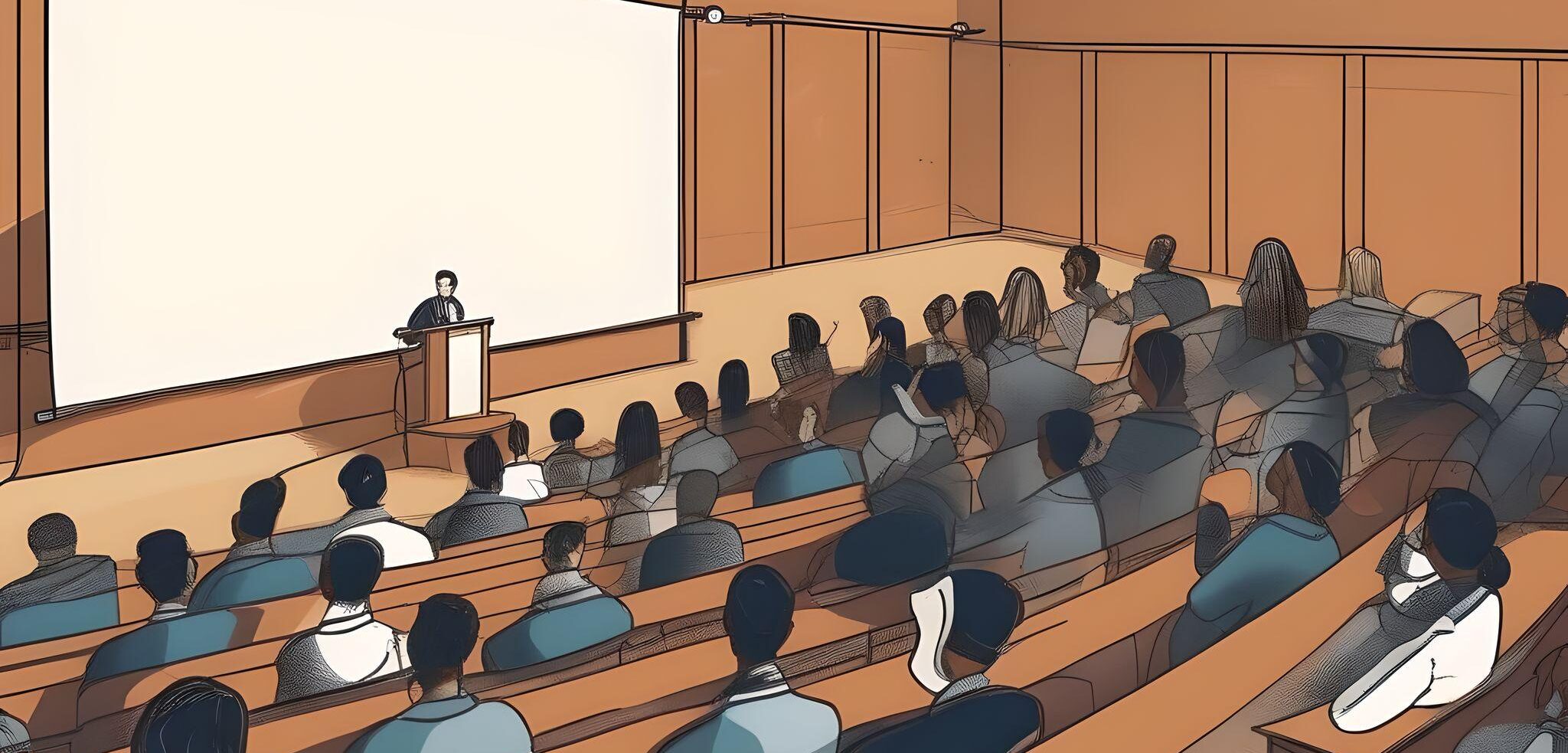最近息子と話をしていて「経験してないことは分からないし、理解してもらえない」ということを改めて認識した。私は民間企業に勤めたことがないので、「企業は最終的には利益優先である」と頭では分かっていても本当には理解できていないような気がする。私は明らかに公務員的発想だし、研究者や教員特有の考え方をしていると思っている。
学会誌の巻頭言で30年前の「大学院重点化」が大学院教育や日本の科学技術低下を招いた可能性があると指摘したが、現在の教員は「大学院重点化」前の研究室や大学運営の状況を知らないので、その頃の方式が良かったといくら主張しても理解できないだろうと思う。また、例えそのことを証明したくても30年必要になるし、良くなるかどうかも分からない。
退職前年に「正式な合格発表前に合格内定者を発表するシステムは新領域創成科学研究科にしかなく、成績集計や発表資料作成までの時間的制約を考えるとやめるべきだ」との指摘が研究科入試委員会で委員や事務方(教務係)からあったと専攻会議で聞いた。実はこの「内定システム」は私が研究科入試委員長の時に苦労の末に作ったものだ。入試問題漏洩事件への対応のために作ったものだが、その本質(志望先教員と受験生の関係)を簡単に理解してもらうことは無理だと思ったので黙って聞いていた。システムを作った当時の入試委員長が私であることは調べれば分かることなので、当時の関係者の意見を聞く必要もなかったのだろうと思った。自分たちが同じ問題を抱えたら初めてその理由が分かるのかもしれない。一方で、現在の先端生命科学専攻の入試システムでは「内定システム」が必要であり、その維持を申し入れることになったのは面白かった。その時々に、それぞれの立場の人達の都合に合わせた結論になるのだと改めて思った。
また、備品管理や経理システムを事務が勝手に変更していることを知った時にも驚いた。事務官は5年も経つと次々と異動して、その部署でシステム(やり方)を教え込まれるために、過去のやり方は知らないし、今のやり方が正しいと思っている。変更したことによって生じる問題点を指摘しても、理解できないので、今のシステムに従うように教員に指示する。コンプライアンス違反の可能性があるし、いずれ破綻してその時には解決するために多大な労力を払うことになるのだが、今担当している事務官はその時には異動や退職して関係なくなっている可能性が高い。定年間近の年配教員が指摘することなどしばらく聞き流しておけば良いと考えているのかもしれない。
私が経験した年金(退職後も在職中の計算になっていた)やマイナ保険証(一ヶ月利用出来なかった)の問題は数ヶ月のうちに解決した。にもかかわらず、なぜしつこく改善を要求するのか事務は理解できないだろうと思う。自分が退職する時に経験したら気づくのかもしれない。これまでの退職者も一時的な問題だったので我慢したために問題が放置されてきたと思っている。私は「過去5年間で問題があったケースを調べあげて、どの段階で問題が生じたか調べて欲しい」と要求したのだが、面倒だったのだろう「今後、このようなことが起こらないよう、人事チームからのご案内方法を再検討し、再発防止に努めてまいります。」との形式的な返事をされただけで終止符を打たれた。このようなことが続いていては「目の前の自分のメリットにならない、面倒なことには手出しをしない」という考え方になる。まさかそんな些細な問題を改善しようと思ったのが都議会議員になろうとしたきっかけだったとは夢にも思わないだろう。どの組織(例えば東京都の共済組合)でも同様なことが起きていると想像している。選挙活動中に国民健康保険への切り替え時にマイナ保険証の利用に問題が起きたと友達が連絡してきた。その友達も「そんな些細なことを気にしているのか」と3月に会った時には言っていたのだが。