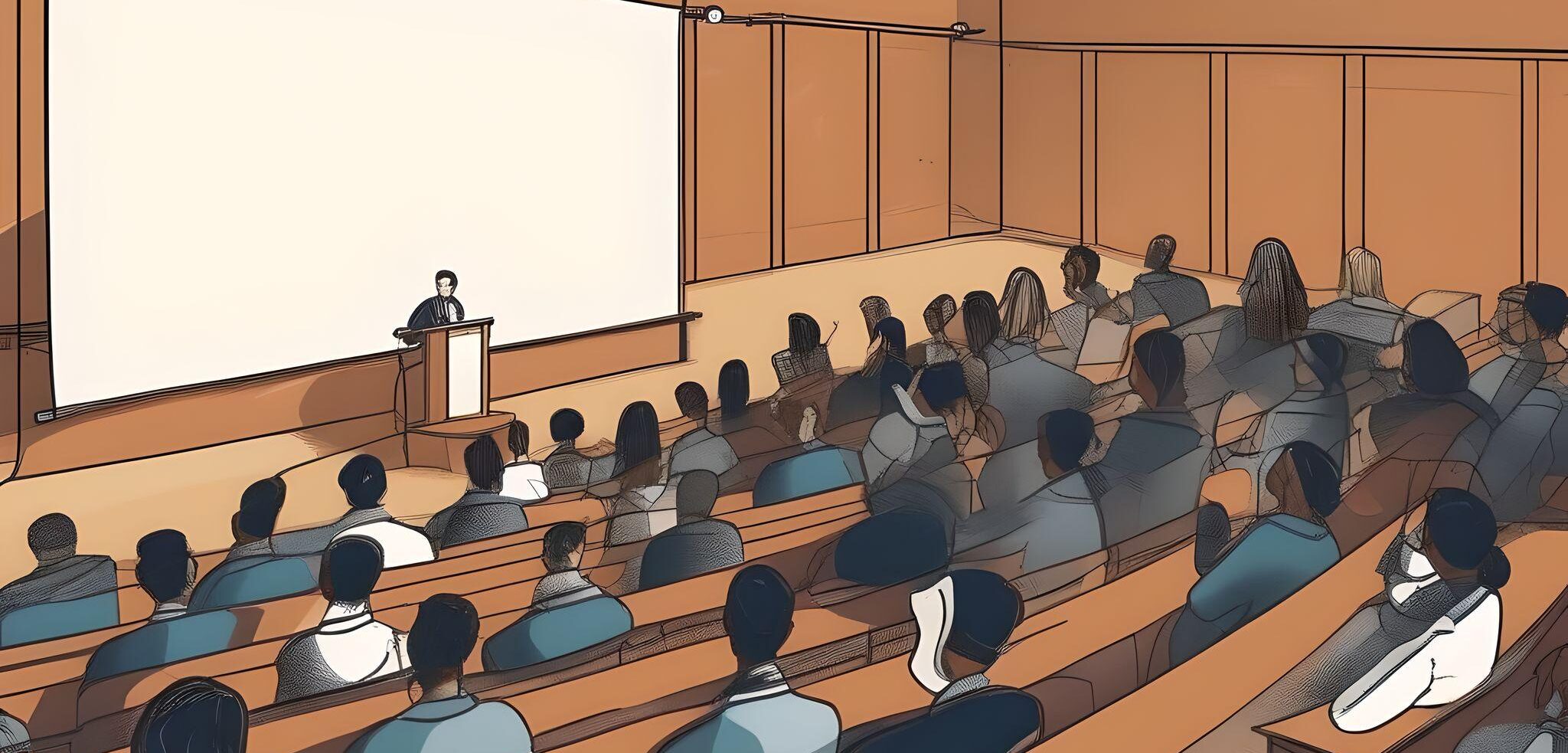科学・学術界では、学会誌など学術誌に投稿された論文を同じ分野の別の研究者が検証(論文審査)して掲載の可否を判定する「査読」とも呼ばれているシステムがある。
論文を投稿して何報か採択されると、査読の依頼が学術誌の編集部から届くようになる。それまでは審査される側だったが、審査するという立場になることになる。そこで陥るのが、自分は偉くなったと錯覚して、高圧的な立場で査読をする若手研究者が多いことだ。「自分が受けたと錯覚している恨み」を晴らそうとする輩もいる。
論文のアブストラクト(概要)を読んでからその論文の審査を引き受けるかどうか判断するのだが、私は論文審査を引き受ける場合は、その雑誌に受理されることを前提にしている。時に本文全体を読むととんでもない論文であることがあるが、その場合はできるだけ早く「科学的な矛盾」をきちんと指摘して「reject(拒否)」の判断を編集者に返事することにしている。その後の判断は著者や編集者に任せることにして、例え修正論文が再投稿されても審査しないことにしている。
審査にあたっては、まず論文の構成がきちんとしていて論理的に書かれているかどうかの判断をする。あまり数は多くないが、論文の内容や結論は正しいと判断できるが、構成に問題がある場合は、どのように書けば読者に分かりやすくなるかコメントして論文を書き直してもらうことにしている。ただ、そのような指摘をすると、受理されるのが難しいと判断して再投稿しない著者が多い。そうではない。科学論文の書き方を知らないので、その指導をしているつもりなのだ。
最近の論文は、細切れ感を感じるものが多い。昔は「実験ばっかりしないで、データも溜まっているのだから論文を書きなさい」と指導教員に言われていたが、最近は実験を少しだけやって「論文を書きたい」という学生や若手研究者が多くなったように思う。論文数で自分の価値が計られていると思っているのだろう。確かに論文数はその研究者の実力を示す面もあるが、内容をきちんと読まれていることに気づいていない。人事審査の最終段階では表面的な数値より実質的な内容を重視していることが多い。
論文の書き方は、執筆の過程で共著者である年長者から指導を受けることになるが、論文審査のやり方は「論文内容を他者に漏らしてはいけない」との規定があるため指導を受ける機会がほとんど無いように思う。指導教員が引き受けた審査論文を読んでコメントを書くことを学び、指導教員がどんな審査結果を編集部に送るのか知ることが必要ではないだろうか? 内緒だが、私は時々やっていた。論文審査も訓練を積まないとうまくならない。